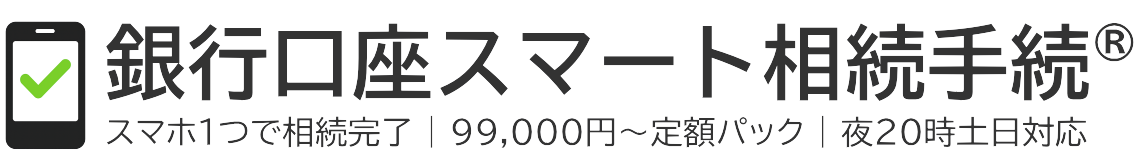第1節 遺言書作成を受任する際の注意点
1.遺言書作成の一般的な流れ
①依頼者との初回相談において、依頼者がどのような内容の遺言を希望しているのか、具体的には自己の遺産を誰に、どのように分けたいのか、依頼者の真意を聴きとらなければならない。そして、依頼者と協議してどのような方式の遺言書を作成するか決定する。
②依頼者の相続関係や財産関係に関する資料を収集し、その資料に基づき、相続関係説明図と財産目録を作成する。
③依頼者の意向に従って、遺言書の文案を作成する。
④その後、依頼者と再度打ち合わせを行い、遺言書案が依頼者の最終意思と合致しているか詰めの作業を行う。
⑤依頼者との協議の末、遺言書案が完成した後は、選択した遺言の方式に従って遺言書を作成する。
例
公正証書遺言の方式である場合は、事前に公証人に遺言書案を送付し、遺言書の文言の最終的な検討を行い、遺言書の作成期日に依頼者と2名の証人を同伴し、公証人役場で公正証書遺言を作成する。
自筆証書遺言の方式による時は、依頼者本人に、遺言書案に基づき、遺言書を手書きしてもらう。専門家は完成した遺言書が方式を具備しているか最終チェックし、問題がないと判断した時は、依頼者に、面前で遺言書を封印させる。
2.事情聴取の際に留意すべき事
①事情聴取の相手は依頼者であり、相続人ではない。
遺言書の作成は遺言者本人から依頼されることが基本であるが、実務では専門家のもとに、遺言者本人のほかに同居している親族などの相続人が同伴する例が多い。また専門家と相続人がもともと知り合いである場合も多い。このような場合は、その親族に遺産の多くが分け与えられる事が多く、時として、その者が遺言者よりも遺言書作成に主導的な役割を果たしている。
専門家はついつい親族と信頼関係を築きやすく、親族が依頼者であるかのような錯覚に陥りやすい。しかし留意すべきことは、専門家の依頼者は遺言者であって親族や受遺者ではないということである。
専門家は、遺言者の真意を確認する上で、家族に席を外してもらうか、別途日時を指定して遺言者一人から事情を聴きとるなどの配慮をする必要がある。あくまでも事情聴取の相手は遺言者その人であり、相続人ではないのである。
②事情聴取に先立ち依頼者にアンケートを実施する
事情聴取の事項は多岐にわたる。専門家は限られた時間内で効率よく必要事項を聴きとらなければならない。そのためには初回打ち合わせに際して、事前に、依頼者に対し簡略なアンケートを実施し、依頼者の家族関係(続柄、氏名、生年月日、住所など)、資産内容、希望する遺産の分配に関する事項を記入してもらっておくなどの工夫が有益である。
③遺言書作成の動機についてもたずねる
事情聴取の中心は、依頼者がどのような内容の遺言を希望しているかという点にある。具体的には、依頼者の有する資産の内訳、相続人の有無およびその内訳、誰にどの資産を取得させたいか、財産の処分以外にどのようなことを希望するか、たとえば、祭祀継承に関する事項、死後の事務処理に関する事項、家族に対するメッセージなどについてたずねることになる。
ところで、遺言書の作成を希望する依頼者の多くは、民法の定める法定相続分や法定相続人と異なる遺産の分配を望んでいる。遺言それ自体に相続人間の争いの萌芽を宿していると言える。
したがって専門家は、なぜ依頼者がわざわざこのような内容の遺言を希望するのか、依頼者の遺言書作成の動機についてもたずねるべきである。また、依頼者が過去に家族に生前贈与を行ったことがあるのか、家族の中に財産増殖、維持に寄与した者がいるのかなど、遺言の周辺部分を把握することができれば、より相続人らの納得の得られる遺言書を作成できる。また遺言の内容が将来、相続人の遺留分を侵害するおそれがあるかどうかをも予測でき、遺言書上で将来の紛争を防止するための種々の工夫も可能となる。
3.状況に応じ遺言方式を柔軟に選択する
遺言書の作成依頼を受けた専門家は、依頼者と協議の上で、どのような遺言の方式を選択するか検討しなければならない。一般に専門家が作成に関わる場合は、公正証書遺言の方式を選択することが多い。これは公正証書遺言が公証人の関与の下に作成される遺言であり、将来遺言の無効を主張される割合が少なく、自筆証書遺言より安全であると考えられているからであろう。
しかし、自筆証書遺言の効力が問題となるのは、専門家が遺言書の作成に関与せず遺言者本人が単独で作成した場合がほとんどである。また公正証書遺言と言えども、遺言能力、口述要件を欠くとして無効とされる裁判例も多く、必ずしも安心できるわけではない。
専門家は依頼者と十分は打ち合わせをした上で、遺言の内容、遺言書作成の契機、依頼者の性格や能力、遺言書の書換えの可能性など、種々の状況を総合的に考慮して、依頼者のニーズに最も叶う方式を柔軟に選択すべきである。
4.十分な資料を準備した上で遺言書の作成に取り掛かる
遺言書を作成するにあたっては、後日、遺言を執行する際に紛争とならないよう、相続財産に関する資料を十分に備えた上で、遺言書の作成に着手することが安全である。たとえば、依頼者と相続人との続柄を示す戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、相続人以外の受遺者の住民票など。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人からこれらの資料を要求されるため、資料を準備せずに遺言書を作成するということはありえない。しかし、自筆証書遺言を作成する場合は、必ずしもこれらの資料は必要とされていないので、ともすれば戸籍謄本や登記簿謄本を準備せずに、依頼者からの話だけから安易に遺言書を作成しがちである。しかし自筆証書遺言と言えども、専門家がその作成に関与する場合は、公正証書と分け隔てなく、相続関係や財産を裏付ける資料を準備した上で作成すべきである。
5.相続関係説明図、財産目録を作成する
遺言書を作成する際には、相続関係説明図や財産目録を作成したほうがよい。これらの書類は法律上、遺言書の作成に必要とされているわけではないが、これらの書類を作成しておけば、遺言書作成にあたり、他の相続人の遺留分を侵害していないか、また主要な財産を遺言書の記載から漏らしていないかチェックすることができる。さらに、作成に関与した専門家がそのまま遺言執行者となる場合には、遺言の効力発生後、相続人らに対する通知や、相続財産目録の作成を速やかに行うことができる。
6.遺言書案を作成する
専門家が依頼者から事情を聴きとり、財産や相続人に関する資料等を収集できた段階で、依頼者の意向に基づき、遺言書案を作成する。依頼者に対し、遺言書案を示して、打ち合わせを重ね、遺言書案を完成させる。遺言書案につき依頼者の了解を得られた後は、選択した遺言の方式に従って遺言書の作成を進める。公正証書遺言であれば、事前に遺言書案を公証人宛に送付し、公証人との間で文言の詰めを行う。
自筆証書遺言の場合は、遺言者に遺言書案を清書させる。遺言書案に基づき自筆証書遺言を作成させることにより、遺言者の負担を軽減させることができるし、加除訂正部分も最小にとどめることができる。また後日、遺言書の意味内容をめぐって相続人間で疑義が生ずることも避けられる。
なお自筆証書遺言の遺言原案は、分量が多すぎるのは好ましくなく、また表現も専門家による専門的な文章を避けることが望ましい。依頼者の目線に立って、平易な遺言書案にするよう心掛ける。
7.遺留分を侵害する遺言書を作成する場合に留意すること
依頼者の希望する遺言内容が明らかに法定相続人の遺留分を侵害している場合、遺言書の作成を依頼された専門家はどのように対応すべきか。依頼者が遺留分制度について理解していない場合、依頼者に対し遺留分制度の趣旨を説明し、できれば遺留分を侵害しない内容の遺言を勧めることが望ましい。依頼者が遺留分制度を理解したうえであえて遺留分を侵害する内容の遺言書の作成を希望する場合は、専門家は依頼者の意向に従って遺言書を作成するほかない。遺留分を侵害する遺言も、相続人から遺留分減殺請求がなされて初めて、遺留分を侵害する限度で無効となるにすぎないからである。
ただし、将来、相続人間の紛争をできる限り回避するためにも、依頼者が特定の相続人に対し多くの財産を分け与える動機や、遺留分権利者に減殺請求権行使しないよう希望する旨を、遺言書の付言事項として記載することを提案したほうが良い。また将来、相続人から遺留分減殺請求がなされることが確実に予測される場合には、遺言書の中に、遺留分減殺の順序を定めておくことも必要である。
8.専門家が遺言執行者の指名を受ける場合
遺言内容が相続人の遺留分を侵害するような場合に、遺言書の作成に関与した専門家が遺言執行者となれば、相続人から遺言執行者としての中立性、公正さを疑われることになる。
また受益相続人や受遺者が他の相続人から遺留分の減殺請求を受けた場合、受任専門家例えば弁護士は受益相続人らから事件を相談される可能性があり、この場合、仮に遺言執行者が受益相続人の代理人として事件を受任すれば、弁護士として「品位を失うべき非行」に該当するとして懲戒自由となる。(平成18年1月日弁連懲戒委員会の決議)
専門家、特に弁護士が遺言執行者の指名をうけるかどうかについては遺言内容に照らして慎重に判断する必要がある。
9.遺言能力が疑わしい場合の対処法
遺言書作成の実際において、専門家が入院中の患者の家族から連絡を受け、遺言書の作成を依頼されるケースがある。この場合、専門家は病院に出張して遺言者と面談し、遺言者から事情を聴くことになる。入院患者の多くは死期が間近に迫っており、中には、正常な判断能力が十分に備わっているかどうか疑わしいケースもある。
専門家は、遺言書の作成を受任するにあたって、本人や担当医師から十分に事情をたずね、依頼者の遺言能力の在否を確認し、遺言能力がないと判断した場合は遺言書の作成を受任してはならない。また遺言能力があると判断した場合でも、作成時には、医師の立会いを求めるべきである。その他、将来、遺言能力が争いになった場合を想定して遺言能力を基礎づける証拠を保全しておく必要がある。
10.証拠を保全しておく
専門家は、将来の紛争が予想されるような場合、遺言書を作成する段階で、遺言の効力を裏付ける証拠を保全しておくべきである。たとえば、前述したとおり、遺言能力を失われそうな場合は医師の診断書等を準備しておくべきであり、また自筆証書遺言において自書を争われそうな場合は遺言者の筆跡を対照する文書(遺言作成時に近接した時に作成された文書で、かつ遺言書と同一字句の含まれた文書)を保全しておくべきである。
遺言の効力に争いが予想されない場合も、死後に遺言者の真意を相続人に伝えるため、遺言書作成にあたり、遺言者が遺言書を作成した経緯や心情についてビデオ等に録画して保存するなどの工夫も有益である。このような遺言者の生の声を収録しておけば、このビデオ映像を見た相続人らは、たとえ自己に不利益な内容の遺言であっても、事実上、納得せざるを得ないし、相続人間の紛争を回避できる可能性が高い。
11.委任契約書を作成する
遺言書の作成を受任するに際して、専門家は依頼者に対し、一般民事事件と同様、料金及び費用について適切な説明を行ったうえで委任契約書を作成しなければならない。
特に注意すべきは公正証書遺言作成にともなう手数料等についての説明である。
公正証書遺言の手数料は、各相続人、受遺者が相続または遺贈を受けた額に対してそれぞれ計算され、その各人ごとの手数料の合計額が作成の手数料総額となる。したがって、遺言の内容がある程度確定した段階で手数料の金額が明らかになるので、初回相談においては公証人の作成手数料概要について説明し、おおよその費用の目安だけでも告げることが望ましい。また不動産が多数あり、相続人も多数存在するときは、登記簿謄本や戸籍謄本の取り寄せに要する費用も多額となるおそれがあるので、概算を説明しておくべきである。
委任契約書を締結する際は、受任する法律事務の範囲も明確にすべきである。専門家が遺言書の作成のほか、遺言書の保管や遺言執行まで受任する場合は、委任時効として遺言書の保管や遺言執行についても明記し、これらの具体的費用も定めておくべきである。なお、委任契約書で遺言執行者の指定、費用を定めても、それ自体として直ちに法的効力を発生させるものではないが、後日、相続人に対する理解を得やすくなるという効用がある。
出典 遺言実務 三協法規